保健指導 |
保健指導、健康教育、健康づくりの進め方など
保健・公衆衛生分野で活動する人のためのコーナー |
| HOME|パーソナリティと健康|行動医学サブテキスト|プロフィール|産業保健|保健指導|発達行動|私の講演・研修|個人差と健康|分子神経行動学研究会|分子神経行動学|京大院医学研究科健康増進・行動学 |
 |
 厚生労働科学研究「効果的な保健指導方法の開発」 分担研究者 朝枝 哲也 厚生労働科学研究「効果的な保健指導方法の開発」 分担研究者 朝枝 哲也 |
〔研究要旨〕 効果的な保健指導に関連して,【研究1】健康診断に対する効果的な保健指導のタイミング,【研究2】適性処遇交互作用,【研究3】自己効力感を促す超低タールタバコ指導法の有効性,【研究4】喫煙に対するイメージによる対象の分類の可能性,【研究5】個人のアルコール感受性に基づく飲酒指導の有効性,【研究6】健診の10年トレンドを用いた指導,【研究7】保健指導法の有効性の比較,【研究8】 social marketingの手法を用いた喫煙に対するプロアクティブアプローチ(禁煙意志のない者も取り込む健康増進活動)法の有効性を検討するとともに,保健指導に関連する行動変容モデルの構築を試みた。また【研究9】自己採血法によるセルフケアの効果について検討する研究を行った。これら9つの研究の結果は,【研究1】健診1か月前の事前指導は有効であり,【研究2】適性処遇交互作用はみられなかったが多くの保健モデルに用いられている期待×価値の保健行動の予測は有効であり,【研究3】自律性や自己効力を促す指導法も有効であった。【研究4】喫煙に対するイメージによって変化のステージ(無関心期・関心期前期・関心期後期・準備期・実行期・維持期)を評価できる可能性が示唆された。【研究5】一方,個人のアルコール感受性に基づく飲酒指導の有効性については効果が乏しく幾つかの課題を残した。【研究6】保健指導のあり方として、有所見に対して実施しがちであるが、労働者の関心は、むしろ肥満や高脂血症などにあり健診の事後措置とは別に健康増進活動を行う上で参考となる。【研究7】超低タールタバコへ切り換える指導の方が、クイックリラックス(瞬間リラックス)法よりも意識の変化も含めて行動変容を有意に促した。【研究8】 social marketingの手法を用いた喫煙に対するプロアクティブアプローチは有効であり,喫煙指導において性格等も考慮したNBM(narrative-based medicine)が重要になると思われる。【研究9】最後に,自己採血デバイスを用いた保健指導は高脂血症有所見者に対して有意にコレステロール値を限界値以上に減少させ,今後,セルフケアを促すために保健指導等において積極的に使用し,長期的な効果についても検討することは医療経済学的にも重要な事項になるものと思われた。 はじめに 健康診断の有所見率は増加の一途を辿っており,特に,中小規模事業場において高い。1)2)これらの大半は,高脂血症をはじめとする生活習慣病に関連したものであるが,こうした有所見者の多くは,自覚症状に乏しく自らは保健行動などの積極的対処行動をとり難いとされている。 そこで,健診の事後措置として産業医や保健師等による保健指導が行なわれるが,対象労働者の行動変容は中々容易なことではない。一方,保健指導を実施する側も,個々が経験的に対応しているだけで,標準化がなされておらず効果的な保健指導方法についてのエビデンスが乏しい。毎年,健康診断に費やされる莫大な費用(投資)に見合う効果が生み出されるようにするためには,効果的な保健指導方法の開発が望まれている。 本研究では特に以下の種々の保健指導に関連する要因や方法について検討を加え,具体的な保健指導方法・技術の有効性について評価した。 【研究1】事前指導の効果 A.研究1の目的 保健指導に関連する要因には,状況,方法,技術・態度など様々なものが考えられるが,その中で保健指導のタイミングについて検討することを目的とする。 B.研究1の方法・対象 (1)中規模事業場(従業員900人弱) において,約1年前の前回健康診断の結果,「要精密検査」と判定された者の中から,脂質検査で連続3回のデータが悪化傾向にあると判断された未治療の男性51名を産業医が選定し,その中から無作為に26名を抽出して,個別保健指導の対象とした。 (2)次に健康診断1か月前に,2人の保健師からそれぞれ13人づつに対して, 次の諸点について留意しながら約10分の保健指導を行った。 ①前回健康診断の結果が,正常範囲からどれだけ逸脱しているか,さらに社内全員の分布の中で自分がどの辺の位置にいるかを一目でわかるように示す。 ②改善の必要性を話す。 ③予め高脂血症改善に効果的とされている12項目を図示しておき,その中から現在できているものとできていないものとに分類させ,既にできてできているものと絶対にできないものは外して,自らできそうだという項目を3つ程度選択させ,次の健康診断までに取り組む目標として実行してもらう。 ④次の健康診断結果について,コントロール群と比較する。 (3)事前指導の効果の追試 ①初年度と同様に中規模事業場(従業員900人弱)において,約1年前の前回健康診断の結果,脂質検査で「要精密検査」と判定された未治療者の中から,BMIが25を超える男性66名を産業医が選定し,個別保健指導の対象とした。 ②次に健康診断1か月前に,1人の保健師から63名全員対して,初年度と同様に(2)①~④の諸点について留意しながら約10分の保健指導を行った。 C.研究1の結果:(1)事前指導対象群は,1か月後の健康診断の結果において,対照群に比して有意にデータの改善が認められた。(図1-1,1-2) (2)事前指導の効果の追試の結果 初年度と同様に事前指導対象群は,1か月後の健康診断の結果において,対照群に比して指導したBMIについて有意にデータの改善が認められた。(図1-3,表1-1) 表1-1 また、脂質検査についても、初年度と同様に対照に比して有意に改善が見られた。(表1-2) しかし、経年的には中性脂肪を除き有改善は見られなかった。(表1-3) 表1-2 D.研究1の考察 高危険群への介入の効果を判定する上で,留意すべき事の一つに「平均への回帰」という現象がある。これは,単発のデータを基に分類した時に生じ易いことから,今回はそれを回避する目的で,脂質検査で連続3回のデータが悪化傾向にあると判断された者を対象とするなどトレンドに基づいて対象を抽出したが,それでも対照群において僅かであるが,全体としてデータはやや改善傾向が認められた。しかし,事前指導実施群は,それ以上に改善していた。両者とも約11か月前には事後指導を受けている事から,少なくとも事前指導は動機づけを得やすく一時的な行動変容を促しうる効果があると言える。 またBMI及び総コレステロール、HDLコレステロールについては、昨年度と同様に有意な改善が見られた。但し、経年的には中性脂肪を除き総コレステロール、HDLいずれも僅かに上昇した。これは、もともとそれほど高いデータでなかったことと、対照群はこれら両者ともがより悪化していることからも効果があったと考えてよいかもしれない。 以上より事前指導は動機づけを得やすく一時的な行動変容を促しうる効果があると言える。この効果がどの程度持続するものかどうか,あるいは健康診断の周期の中でどのタイミングで実施するのが効果的であるか今後の検討課題である。 E.研究1の結論 初年度及び今回の結果より、少なくとも脂質検査領域の高危険者若しくは肥満者においては,健康診断1か月前の事前指導は,動機づけを得やすく健診の有所見率を低減する効果が得られる。 但し,健診の際に指導対象者からは,「今でも続いている」「これからも出来そうだ」などの積極的な声が聞かれているものの,この効果がどの程度持続するものかどうか,あるいは健康診断の周期の中でどのタイミングで実施するのが効果的であるか今後の検討の余地が残されており, 以下のように今後比較してみることが有用と思われる。 |
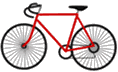 |
 |
 【研究2】適性処遇交互作用 【研究2】適性処遇交互作用 |
A.研究2の目的 効果的な指導を行うためには,個々の特性を考慮する必要がある。この点に関連して行動科学では,個人の人格変数としてのLocus of Control(LOC)に応じた教育・指導を行うことによってより大きな効果を期待することができるとされ,適性処遇交互作用(Cronbach,1977)と呼ばれている。3) 本研究は,この適正処遇交互作用がみられるかどうか検討することを目的とする。 B.研究2の方法及び対象 (1)健康関連行動に関するモデルとして現在「統合化モデル」(図2)が提唱されておりRotterの行動予測モデル=「期待×価値」モデル4)を基礎としていることから,保健行動の予測変数として結果期待の指標であるHealth Locus of Control(以下HLCと略す)と価値観を知る目的で健康,友人,家族,異性,仕事,お金,趣味,ボランティア活動, 環境問題等選択する設問を用いた。 (2)中規模製造業の従業員723人に,健康教育2カ月前にWallston(1978)らが最初に開発したものを東大の健康教育学研究室の渡辺 (1985)が開発したHLC尺度(14問版)を用いてInternalとExternal,Moderate(中間傾向)の3型の判定を行った。5)6)また予めブレスローの7つの健康習慣7)についても尋ねた。 (3)次に無作為に適性処遇教育群(547人)と対照群(176人)に2分し,さらに適性処遇教育群をHLCの種別とそれに対応する教育プログラムの組合せによって 18組の30人前後の小集団に分類した。 (3)一方,教育内容を標準化する目的でそれぞれのHLCに対する3種類の健康教育プログラムをマルチメディアによって開発した。内容は,いずれもブレスローの7つの健康習慣7)を啓発することをねらいとしたものだが,Internal用プログラムは自ら考えさせるとともにグループダイナミックスを期待した内容に,Moderate用は自ら考えさせるように,External用は結論強制的なプログラムになるように工夫した。これは,Internalがセルフケア行動に,Externalがコンプライアンス行動に向いているとされているからである。 (4)教育時間は1時間,全て同一講師がほぼ同時期(1週間)実施した。18回実施。 (5)適性処遇教育群・対照群ともに教育直後にブレスローの健康習慣の中でどれが実行できていないか,今後改善する意欲について4段階の回答を求めるアンケートを実施した。 (例)喫煙:「非常に困難」「やや困難」「やや改善する気あり」「かなり改善する気あり」 ここで,ブレスローの7つの健康習慣については健康教育実施2か月前と健康教育直後の2度実施したことになるが,総合指導時はブレスローの7つの健康習慣について教育されないまま回答しており,健康教育直後はブレスローの7つの健康習慣を認知して回答している点で異なったものであることに注意する必要がある。これにより,生活習慣調査の質問紙による妥当性がある程度確認可能となる。 <教育効果の評価方法> 上記の単発の質問だけで,教育前後による効果を評価するのは困難であるため様々な対照群(コントロール)を置いた。なぜなら,対照がなければ教育の効果なのか単なる健康意識の差なのかが判別できないからである ① 基準コントロール:健康教育前に同様の調査を実施(この場合,ブレスローの7つの健康習慣については説明せずに,記入の仕方のみ説明する。) ② 相互コントロール a.プログラム間:3種類のプログラムによる差 b.HLC間:3種類のHLCによる 差 c.項目間 :7つの習慣別の差 ◎強調項目:「朝食」「喫煙」「運動」「睡眠」 ◎空白項目:「肥満」 ◎基準項目:「間食」「飲酒」 ※特に,喫煙についてはタール50mg/日にするように指導した。(【研究3】参照) (6)教育の効果をブレスローの健康習慣 それぞれに対する回答状況の分布に対してχ2検定を実施した。また同時に対照群を基準とした幾何平均を求め「効果得点」とした。 C.研究2の結果 (1)ブレスローの健康習慣の教育を実施した群は,対照群より全ての項目について有意な教育効果を認めた(図2-1)が,特に強調した朝食・運動・喫煙については前二者において効果は顕著であったが,喫煙者については困難であることを伺わせた。 (2)また教育プログラム間にも有意な差を認めIプログラム,Mプログラム,Eプログラムの順に効果的であったが意図的に触れなかった肥満についてはプログラム間の差を認めなかった。 (3)さらにHLCのタイプ間にも有意な差を認め Internal,Moderate,Externalの順に意識の変容が認められた(表2-1,図2-2) (4)しかし適性処遇作用は認められなかった。(2-3図) D.研究2の考察 HLCは,Rotterの社会的学習理論に基づくLOCを保健行動に応用したものであり,HLCがInternal(内的統制傾向)である者は健康は自分自身の努力によって得られると信じ,External(外的統制傾向)の者は医療従事者や運によって得られると信じていると言われている。 期待した適性処遇作用は認められなかったが,教育プログラムの内容によって教育効果に差が生じることが確認された。特に小グループによる考えさせる教育が Internal・Moderateには適していると考えられた。一方 Externalについてはグループにすることは必ずしも効果的とは言えない結果を得たが,この場合でも結論強制型教育より自ら考えさせるようなプログラムの方が効果的に思われた。 E.研究2の結論 以上より,健康教育を実施する上で,HLCは有用な情報を提供するとともに,自ら考えさせるような教育プログラムが一方向の学校教室式の教育プログラムより優れている。 |
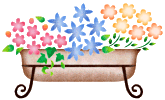 |
 |
 【研究3】超低タールタバコ指導 【研究3】超低タールタバコ指導 |
A.研究3の目的 喫煙指導は,主に禁煙を前提に行われている。しかし,行動医学の諸原則からみるとこのアプローチ法は,幾つかの点において効果的な方法とは言い難い。実際,禁煙の意志が強い者に対する根気の要る禁煙プログラムの成功率でさえ30%を超えないと報告されていることからも理解される。さらに,こうした禁煙の意思を持つ対象者に対するアプローチはリアクティブ・アプローチ法と呼ばれているが,喫煙者の約5割は,全く喫煙をやめようと考えていない人であることを踏まえるとこうした人達も積極的に取り込むプロアクティブ・アプローチ法が求められている。8) そこで行動医学の諸理論に合致していると考えられる超低タールタバコを推奨する喫煙指導法についてその有効性を検討した。 B.研究3の方法と対象 ①外来指導:健康診断の胸部×線検査で「要精密検査」となって呼吸器科外来を受診した者で軽微な異常のみで1年後の経過観察となった者66名に対して,医師による約3分の超低タール喫煙指導※を実施しその効果を1年後に喫煙状況と携帯しているタバコによって医師が確認を行う。 ②健康教育:研究2において,1時間の健康教育の中で約10分程度の超低タール喫煙指導を行なう。まず超低タールタバコのテレビCMのVTRを5分間見せてタール量に関心を持たせた後,講師がタバコの有害性(ブレスローの7つの健康習慣中ワースト1等)とタール量3mg以下の超低タールであればがんリスクはかなり低減すると報告されていることに触れ,禁煙できないのであれば超低タールタバコに切り換えることのメリットについて5分間話した。またこの時,表示タール量×1日喫煙本数が50(mg・本)を超えないようにという明確な基準を伝えるとともに超低タールタバコであっても副流煙はかえって有害なため空間分煙を守るように指導した。約1年後の健康診断時に看護職による問診によって超低タールタバコ指導の効果を確認した。 ③個別指導:保健師等が常駐しているような中規模事業場(東京2,京都2,福岡1事業場)において,超低タール喫煙指導※を保健師等が実施しその効果を1年後に喫煙状況と携帯しているタバコによって保健師等が確認を行う。 〔超低タール喫煙指導内容〕 明確な行動基準の導入(セルフレギュレーション)を行う。 『あなたの今吸っているタバコの銘柄は何ですか?タールはいくらかご存知ですか?と尋ねた上で「タール×1日喫煙本数を50mg/日までにすれば,がんのリスクはほとんどなくなりますよ」と教示し,烙印からの免罪符を与える。同時に,低タールタバコほど周囲に有害であることも教え,分煙マナーを守るように促す。』 ④喫煙状況調査:様々な業種・規模の事業場を対象として,従業員の喫煙状況,特に喫煙者については,そのタバコのタール量について調査を行なった。 C.研究3の結果 (1)外来指導:対象の特殊性があるものの極めて高い効果を得た。1年後禁煙していた者は11人(16.7%)であり、超低タールタバコに切り換えていた者を含めると52人(78.8%)あった。(表3) 尚,ヘルス・ローカス・オブ・コントロールの別では,予測された通り「内的統制傾向」の者の方が「外的統制傾向」の者よりも禁煙率及び低タールタバコへの変更率が高かった。(図3) また1日喫煙本数が20本以上すなわち,2箱吸う者には外的統制傾向の者が多い。 (2)健康教育 1時間の健康教室における10分の超低タールタバコに切り換える集団指導の効果を一年後,喫煙者316人について調べた。禁煙者は年代が高くなるにつれて増加し,50才代では実に15%に達していた。(表3-1)(図3-1) (3)個別指導 保健師が常駐している中規模事業場(3地域、6事業場)における指導結果(表3-1)(図3-2) 全体として、禁煙率15.4%、超低タールタバコへ切り換えた者も含めると、42.3%であった。指導者が変わっても、場所が変わってもほぼ同様の効果が得られた。 D.研究3の考察 約3分の超低タールタバコへの切り換え指導により容易に行動変容が得られた。特に、呼吸器科医による外来時の同じ指導と同等以上の効果が確認された。これは,一般に医療機関において禁煙外来と呼ばれる有料でかつ用意周到に30分以上かけた禁煙指導を受けた時の成績よりやや低いものの15)、自然禁煙率4%をはるかに上回る結果であった。また,通常の医師による禁煙指導の効果7%の倍であった。さらに,禁煙率よりも,低タールタバコへの変更率は,30代で35%にも達していた。尚,禁煙成功者の大半はもともと低タール喫煙者であったことは示唆的である。また、超低タールの銘柄に変更後においても喫煙本数は変わらなかった。 喫煙指導の方略を考える上でまず重要な事は,喫煙が嗜好なのか嗜癖(ニコチン中毒)なのかという問いかけである。1日50本以上の喫煙者が1%もいないことや大多数の喫煙者が20本以下であることあるいはタバコの価格を2倍にすればその需要は劇的に減少する(経済学で云う「弾力的」消費物)と考えられており,こうした事実は大多数の喫煙者にとって喫煙は嗜好の一つと考えるべき証左であろう。 一方,強化の相対性原理と呼ばれるPremackの原理16)によれば,喫煙は喫煙者にとって生起確率の高い行動であるため強い強化子の一つと考えられる。また「反応遮断化理論」12)「行動調整理論」13)によれば,「制限されない(ベースライン)状態において動物(人)が自分の行動を配分する方法が,最も好ましい時間を過ごす方法(「至高点」と呼ばれる)であり,動物(人)はこの状態が制限される時はいつでもできる限り至高点に近づくようにその行動を再配分しようとする」とされている。この考え方に基づけば,喫煙者にとって「喫煙行動」は一つのシステム(反応の連鎖)であり,全行動の中で常に一定のエネルギーが喫煙に対して分配されていることになる。従って,「時間分煙」による喫煙消費量の減少は期待できそうにないし,特に「禁煙」はシステムとして極めて不安定な状態をもたらすためその維持が困難であり,同時に他の強化子行動(食・飲酒等)の増加を促すことになる。また本数を減らす「減煙」が12本より低下させることが困難である理由も理解しやすい。逆に超低タールタバコへの変更は,自己制御についてのAinslie-Rachlin理論19)における「先行拘束」や「反応連鎖において一次強化子(喫煙行動)から最も遠くにある反応ほど崩壊しやすい」ことに合致していることや残りの連鎖に変化がないこと等から,誰にでもできそうだという「効力期待」を抱かせやすい利点がある。また「タール50mg以下にすれば発がんのリスクをかなり低下させ得る」という教示は,セルフレギュレーションにおいて重要とされる明確な行動基準の導入を促す利点がある。実際,禁煙の意志の有無にかかわらず容易に行動変容が得られた。従来「低タールタバコへの切り換え」だと自己調節によって深く吸引したり,本数の増加により各種データ(血中一酸化炭素濃度等)に差が見られないとする報告やあるいは肺がん罹患リスクを軽減しないとする報告がなされてきたが,それらはタール量7mg以上である場合がほとんどである。ここで言う「超低タールタバコ」とはタール量は少なくとも3mg以下であり、特に1mgを指す。以上より超低タールタバコ指導により容易に比較的リスクの少ない低タールタバコへと行動変容が促され,やがて禁煙へと導かれて行くことが期待できる。 E.研究3の結論 以上より,超低タールタバコ指導への切り換えを促す喫煙指導は誰にでも容易であるばかりでなく非常に効果的であり、自己効力感を増大させることによりやがて禁煙へと導き得る優れた指導法であると思われる。 |
 |
 |
 【研究4】喫煙イメージ法によるステージ評価 【研究4】喫煙イメージ法によるステージ評価 |
A.研究4の目的 「喫煙」についてのイメージを喫煙者,非喫煙者,卒煙者に対してイメージ微分法(SD法)9)を用いて分析し,行動の変化のステージ(無関心期・関心期前期・関心期後期・準備期・実行期・維持期)等との関連を検討することを目的とする。 B.研究4の方法と対象 ① パイロットスタディ (1)地域で行われたイベントに参加した者90人(男性61名,女性29人,平均年齢62.6才)を対象に自記式質問紙にて喫煙に対するイメージについて尋ねた。比較的高齢者を対象にした理由は,卒煙者の禁煙後の年数によるイメージに違いがあるかどうかを検討するためである。これ以外にも約9000人に調査した。 (2)質問紙の内容は,喫煙のイメージについて,「個性のある」-「個性のない」,「大人っぽい」-「子供っぽい」等の形容詞対ごとに5段階で評定させる形式のものである。これは,SD法と呼ばれる手法で本来は言語の意味の測定法として開発され,あらかじめ用意されたいくつかの形容詞対ごとにその印象を評定し,その対象に対して対象者が抱く印象(イメージ)の構造や対象者間の関係などを分析しようとするものであるが,近年,商品開発等における消費者の商品に対するイメージを測定する事などに盛んに応用されている。 今回使用したものは,最初に25個の形容詞対のものを独自に作成し,保健学専攻の大学生等約150人に予めテストした結果を因子分析によって12個に絞り込んだものを使用した。 (3)まず①喫煙のイメージについての項目 を変数として主成分分析を実施した。 次に②主成分得点を求めて因子構造上に対象者の位置が視覚的にわかるように図示した。 ③対象者の主成分得点上の分布と等質分析結果から対象者をグループに分け,そのグループ間で喫煙状況を比較した。 ④パイロットスタディで得られた傾向の検証を年金受給開始者に実施した。尚,今回男性についてのみ検討した。 C.研究4の結果 ① パイロットスタディ (1)対象者の喫煙状況は,喫煙者13名(21.3%),卒煙者32名(52.5%),非喫煙者16名(26.2%)であった。 (2)主成分分析の結果,2主成分を抽出(累積寄与率:55%)し,また対象者は喫煙に対するイメージの相違によって,4つのグループに分けることができた。 「愛煙派」とでもいうべき「喫煙グループ1」は喫煙者が最も多く,その1本当たりのタール量の平均値は最も高く,卒煙者においては比較的禁煙後の経過年数が短い傾向がみらた。 また「嫌煙派」とでもいうべき「非喫煙グループ2」は喫煙者は存在せず,卒煙者であれば禁煙後の年数が4つのグループの中で最も長く約20年であった。 「喫煙グループ2」と「非喫煙グループ1」の喫煙者のタール量,卒煙者の禁煙年数は図の通り「喫煙グループ1」と「非喫煙グループ2」のそれぞれ中間であった。 ②検証調査:さらに,研究4で得らた喫煙に対するイメージに関する2つの主成分の有効性を検証するために,ほぼ年齢が60才で均質でかつ様々な個人属性を持つ年金受給開始者を対象自記式質問紙で,喫煙状況および喫煙について「かっこうよさ」と「リラックス」についてのイメージの有無について調査し,男性の有効回答171名を対象に検討した。 (1)対象者の喫煙状況は,喫煙者62名(36.3%),卒煙者54名(31.6%),非喫煙者55名(32.2%)であった。 (2)この中で「かっこういい」というイメージに対して「はい」と回答した者は,僅かに2人であったことから「喫煙はかっかっこういいイメージがありますか?」という問いかけには抑制がかかる傾向があるものと思われ,第一主成分をまとめる表現については再度検討が必要であると思われた。 従って,この調査ではこの質問に対して「どちらでもない」という回答をした者を「かっこういい」というイメージを持つものとして処理した。 (3)その結果,同じ喫煙状況によっても喫煙に対するイメージが異なることが伺われた。特に,喫煙者はほとんどの者がリラックスのイメージを持っているのに対して,卒煙者及び非喫煙者は「リラックス」のイメージがない者が多く見られた。 D.研究4の考察 ①パイロットスタディ:(1)因子負荷量の大きい項目に着目すると,第一主成分は,「かっこよさ」,第二主成分は「リラックス」を表していると考えられる。 (2)また喫煙に対するイメージによって4種類のタイプに分類できることが示唆され,第一のタイプは,図の中心よりやや右下に位置する「喫煙グループ1」であり,喫煙に対して「かっこよさ」と「リラックス」の両方の肯定的イメージを持つ「愛煙派」とでもいうべきタバコ好きの者と考えられる。第二のタイプは,図の中心より左下に位置する「喫煙グループ2」であり,喫煙に対するイメージは,「かっこうよさ」に対しては否定的イメージを「リラックス」に対しては肯定的イメージを持っているタイプで「喫煙消極派」とでもいうべき「タバコをやめたい」タイプと思われた。また,第三のタイプは,図の中心より右上に位置する「非喫煙グループ1」であり,喫煙に対するイメージは「かっこうよさ」や「リラックス」に対して肯定的イメージを持つ「喫煙懐古派」とでもいうべき,タバコに懐かしさを未だ抱いている卒煙者と考えられ,第四のタイプは図の左上方に位置 する「非喫煙グループ2」であり,喫煙のイメージに対しては「格好よさ」と「リラックス」に対していずれも否定的イメージを持つ「嫌煙派」とでもいうべきタバコ嫌いであり,卒煙者であれば禁煙して非常に長く経っている者であった。 以上,喫煙についてのイメージに個人差があることが認めら,特に2つのイメージにより喫煙態度を分類できる可能性が示唆された。行動科学における記憶のイメージ・ネットワークモデル11)によればイメージの差こそが行動等の個人差をつくりだすものと考えられている。 喫煙行動の予測モデルの代表的な一つであるFishbeinの理論の有効性を検討した加藤ら(1985)の報告によると,「喫煙を継続するかあるいは節煙・禁煙するかは,喫煙に対する態度(喫煙結果についての信念及び評価)と大きくかかわっている」としている。 今後,喫煙についてのイメージ分類が,個々の喫煙に対する態度やステージ(無関心期・関心期前期・関心期後期・準備期・実行期・維持期)とどのように関連しているのか,あるいは喫煙の経過とともにイメージの変容があるのか,さらに,例えば「リラックス」のイメージのみの者に対しては,他のリラクゼーションや気分転換方法への切り替えについての指導を行う等,イメージ分類に合わせた効果的な喫煙指導を開発して実際に有用か否か検討する(研究6) |
 |
 |
 【研究5】個人リスクに基づく飲酒指導 【研究5】個人リスクに基づく飲酒指導 |
A.研究5の目的 近年,飲酒は喫煙などその他の生活習慣と同様に多くの疾患の発生作用に影響を与えるものの、すべての飲酒者がアルコール関連疾病に罹患するわけではなく,個人の体質も罹患発生に関与するものと考えられるようになってきた。 そこで,アルコール代謝酵素に関連するアルデヒド脱水素酵素の3つの遺伝子型のうち,1/2型が食道がん等のハイリスクグループであるとする疫学知見に基づき,1/2型と思われる労働者に対して,節酒を促す飲酒指導の効果を検討する。 B.研究5の方法と対象 (1)研究3の個別指導において実施した。すなわち保健師等が常駐しているような中規模事業場(東京2,京都2,福岡1事業場)において,個人リスクに基づく飲酒指導※を保健師等が実施し,その効果を3月,6月,1年後の飲酒状況について保健師等が確認を行う。 ※個人リスクに基づく飲酒指導 ①問診により,アルデヒド脱水素酵素の3つの遺伝子型(1/1型,1/2型,2/2型)を概略判定する。 具体的には,以下の判定表10)に基づく個別指導時に,対象者に示した図1/2型のがんリスク(竹下教授作成資料,和歌山医大)を以下に示す。C.研究5の結果 (1)【研究3】において保健師が常駐している中規模事業場(3地域、6事業場)における指導結果は(表5-1)(図5-1)の通り。 (2)【研究3】の健診時指導においてアルコール感受性に基づく飲酒指導の結果は、(表5-2)(図5-2)の通り。アルコール感受性については、竹下(和歌山医大)の開発した問診表を使用し飲酒できない人を2/2、飲酒習慣がありスコアーが3.1以上を1/2のresponderと見なした。 表5-2(1~6の内容は図7に対応し1は不変) 減量した者で有意であった。(p<0.01) D.研究5の考察 全体として、アルコール量を減量した者の率(減量率)は、19.2%であり、どの地域・事業場においてもほぼ同じ効果が得られた。非常に短い指導の割には効果があったと言えるかもしれないが、保健指導者自身が確認しているために、申告内容について信頼性が乏しいと言える。 また、少なくとも1か月後においては、アルコール感受性指導は、効果があると言える。ALDH2遺伝子型は顔面紅潮により日本人になじみの深い遺伝素因であるが,欧米人には極めて珍しいことが知られており,この遺伝子タイプの者が多量飲酒すると,食道癌等の相対危険度が非常に高くなることから今後,飲酒指導において考慮されるべき事項になるものと思われる。 |
 |
 |
 リンク集 リンク集 |
 アット・ホームページ アット・ホームページ |
ホームページ開設サービスです。 |
 @nifty @nifty |
@niftyのトップページです。 |
 サクサク作成君 サクサク作成君 |
カンタンホームページ作成ツール。 |
 |
| HOME|パーソナリティと健康|行動医学サブテキスト|プロフィール|産業保健|保健指導|発達行動|私の講演・研修|個人差と健康|分子神経行動学研究会|分子神経行動学|京大院医学研究科健康増進・行動学 |
|
