|
�s����w�T�u�e�L�X�g
|
�s����w�ɂ��Ă̊�b�I�����ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă��܂��B
|
| HOME�b�p�[�\�i���e�B�ƌ��N�b�s����w�T�u�e�L�X�g�b�v���t�B�[���b�Y�ƕی��b�ی��w���b���B�s���b���̍u���E���C�b�l���ƌ��N�b���q�_�o�s���w�������b���q�_�o�s���w�b����@��w�����Ȍ��N���i�E�s���w |
 |
 �s����w�T�u�e�L�X�g �s����w�T�u�e�L�X�g |
|
���s����w�Ƃ͉����H
�͂��߂� �`�s����w�I�A�v���[�`�̕K�v���ɂ��ā` �t���I�ł͂��邪�C�l�͂����Ύ����̍s�����R���g���[�����邱�Ƃ�����ł���B�u�ߐH�v�u�߈��v�u�i���v�Ȃǂ��l����Ηe�Ղɗ��������ł��낤�B�ŋ߂܂ō������C���A�a���͐��l�a�ƌĂ�Ă������C�����K���a�ƌ����������悤�ɂȂ����B����́C�����̎�������`�v��������ɖ����̐H������^���C�n�D�C�������̐����K���ɂ���Ĕ��ǂ���Ƃ����v�z���痈�Ă���ƌ����邾�낤�B���̎v�z�̐^�U�͉��ɒu���Ƃ��āC����ł͂��́u�K���v�Ƃ͂ǂ̂悤�ɂ��Č`�������̂ł��낤���H���邢�́C�s���N�Ƃ����K�����Ȃ���߂邱�Ƃ�����Ȃ̂ł��낤���B�����Ăǂ̂悤�ɂ���������������K����ϗe�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł��낤���B�ی��E��ÂɌg���҂��Œ�m���Ă����Ɩ𗧂s����w�̊�b�ɂ��ďq�ׂĂ݂悤�B �i�P�j���N�m���̍����s�������������q�ƂȂ�B�i�s���̑��ΐ����_�j �o�������������̌����ɏ]���C�ꎟ�����q�ɂȂ���̂́u���N�m���̍����s���v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�̂ǂ̊����������ɂƂ��ċ����q�Ƃ́C���ł͂Ȃ������s���ł���C�q���ɂƂ��ċ����q�Ƃ́C��������ł͂Ȃ���������ŗV�ԍs���Ȃ̂ł���B�u��萶�N�m���̍����s���́C��萶�N�m���̒Ⴂ�s������������B�v�̂ł���B�t�̊ϓ_����́u��萶�N�m�����Ⴂ�s���́C��萶�N�m���������s������v���ƂɂȂ�B�]���āC�uPremack���̋����q�v�Ƃ́C�{��ǂށC�g�����v������C�F�l�ɓd�b��������C�e���r������Ȃǂł���B�]���́C����͂����i�g�[�N���G�R�m�~�[�j��H�ו����ƍl�����Ă����B�������D�����q�Ƃ͕����̂��Ƃł͂Ȃ��s�ׂ̂��ƂȂ̂ł���B����ɂ���āu�l���v��������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���镪���a�̊��҂ł́C���ꂪ�u�֎q�ɂ����v���Ƃł������ƕ���Ă���悤�ɂ���l�ɂƂ��Ă̋����q�̃��p�[�g���[��m���Ă������Ƃ͏d�v�ł���B�u�����q�����[�v��p���邱�Ƃɂ���ėe�Ղɒm�邱�Ƃ��ł���B�i���҂ɂƂ��āC�i���s�������炩�ȋ����q�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͋^���悤�̂Ȃ����Ƃł���B �i�Q�j�̂ɂƂ��Ď����̑S�s���͓K�ɕ��z����Ă���B�i�s���G�l���M�[�ۑ����j �u�����Ւf�����_�v�ł́C�u�Q�̍s����������������Ȃ��Ƃ��Ɣ�ׂĐ��������ƁC��萧�����ꂽ�s���͂�萧���̏��Ȃ��s���̋����q�Ƃ��ē����v�Ƃ����l������ �u�s���C�����_�v�ł́u��������Ȃ��i�x�[�X���C���j���Ԃɂ����ē����������̍s����z��������@���C�ł��]�܂������Ԃ��߂������@�ł���v�ƍl�����Ă���C���̏�Ԃ��u�����_�v�ƌĂ�ł���B�����̍s�������炩�̃X�P�W���[���̗v���ɂ���Đ����Ƃ��͂��ł��C�ł�����莊���_�ɋ߂Â��悤�ɍs����z������B �Ƃ���C�u�����v�ƌĂ�ł����ߒ��́C���ۂɂ͈�̓���̔��������߂Ă���̂ł͂Ȃ��āC�ނ�����ɂ���ċ������ꂽ����Ɂg�K������h���߂ɍs���̎��Ԃ��Ĕz�����Ă���̂ł���B�Ⴆ�C�i���s���𐧌�����ΕK�����̍s�����������邱�Ƃ��ώ@�����ł��낤�B���邢�́C�x���ɂ��낲�낵�Ă���҂ɐV���ɉ^���������邽�߂ɂ͍s���S�̂�����K�v������B����ɗގ��������ۂƂ��āC�u�v���m���Ă���B��������Ȃ��Ȃ������߂ɂ��锽�������ʂ������C����ȑO�Ɋw�K���Ă����s�����u�v����B �i�R�j��ʊw�K�����Ǝ���L�̊w�K�i�s���V�X�e�����j �ǂ̂悤�ȓ����ł��C�ǂ̂悤�Ȏh���ł��C�ǂ̂悤�Ȕ������Ώۂł����Ă��C�����Â��i�w�K�j�������悤�ɐ�������̂ł͂Ȃ��B��ŗL�́C�����w�I�Ɍ��肳�ꂽ�A���\��������C�w�K�̗l�����قȂ��Ă���B�Ⴆ�C�u�K���V�A���ʁv�Ƃ��ėL���ȃl�Y�~�̖��o�����w�K�ł́C�u���o�v�Ɓu�~���Ǝˁi�Óf��p�j�v�C�u���v�Ɓu�d���v�Ƃ̊ԂŌ����w�K���������邪�u���o�v�Ɓu�d���v�C�u���v�Ɓu�~���Ǝˁv�Ƃ̊Ԃł͐������Ȃ��B���l�ɃI�y�����g�����Â��̎h��������ɂ����Ă��ώ@����C���̏ꍇ�ɂ͎��o�h�����K���Ă���B���邢�́C�I�y�����g�����̕ϗe�\���́C�㑱�̋����q�Ƃ̐����w�I���������݂��邱�Ƃ�����Ă���B���邢�̓I�y�����g�����Â��s���̕���Ƃ��Ēm���Ă��錻�ۂ�����B����́C�I�y�����g�w�K���������ɐ��T�Ԃ��琔�J����Ɍ����s���̕ω��Łu�{�\�I��E�v�ƌĂ�Ă���B�����͎�ɓ��L�̍s�����p�[�g���[�ɒu��������Ă��܂��B�܂��C������ɑ����Ă��Ă��C���B�i�K�ɂ���āC�܂������ɂ���ĉ\�Ȋw�K�Ƃ����łȂ��w�K������C�u�ՊE���v�ƌĂ�Ă���B�L���ȃJ���̐��́u���荞�݁v�́C�z����P�R���Ԃ���P�U���Ԃ̊Ԃł̂ݐ������邵�C�l�R�̎��o�͐���U�T����W�T�̊Ԃɐ�������Ƃ���Ă���B�l�̌���w�K�ɂ��u�ՊE���v������ƌ����Ă���B ���������w�K�ɑ��鐶���w�I�����������邽�߂Ɂu�s���V�X�e�����v��������ꂽ�B����́C�����́C�n�������I�Ɂu�H�a�Ɋ֘A�����s���V�X�e���v�u�����s���Ɋ֘A�����s���V�X�e���v�u�g���������߂�s���V�X�e���v�u��z�s���V�X�e���v���ȂǗl�X�ȍs���V�X�e���B������悤�ɗ\�ߎd�g�܂�Ă���Ɖ��肷��B����܂ŏq�ׂĂ����w�K�́C�̔����I�Ȋw�K�ƌ����悤�B���Ȃ킿�C�����������̍s���̗B��̌���v���ł͂Ȃ��C��`�I�v�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B �i�S�j���ׂẴ^�C�v�̊w�K�̈Ӗ��́C�����ɂ��āu���_�v���邱�Ƃɂ���B �u�鉻�v�ł́C���x���J��Ԃ����h���Ɏ���ɔ������Ȃ��Ȃ��Ă����o�߂����ǂ邪�C���������Ă���ł��낤���_�́C���̎h��������ȏ�̈Ӗ��������Ƃ͂Ȃ��ł��낤�Ƃ������Ƃł���B���̈ꌩ�P���Ȋw�K�ɂ�����`�q��_�o�������֗^���Ă��邱�Ƃ��ؖ�����Ă���B�����ߒ��̂��ߒ��ł̓h�[�p�~�����C���ߒ��ł̓Z���g�j��������������Ă��邱�Ƃ��ŋ߉𖾂��ꂽ�B���l�ɁC�ÓT�I�����Â��ɂ����Ă������͉ߋ��̌o���Ɋ�Â��Ăǂ�ȏd�v�ȏo�������b�r�ɑ����̂��ɂ��Đ��_���Ă���悤�ł���B�\���ʂ�ł���Ɗw�K���ʂ��Ȃ��C�\���O�ł���Ɗw�K�����B�v����ɍs���́C�����q�ɑ���\���ɂ���Đ�����B���̂S�̓�����L����B �@�u�ڕW�w���I�v�ł��� �A�u�����I�����A���v�u�w�K�������A���v�̂悤�ɃV�X�e��������Ă���B �@�@���锽���̐��s�����̔����ٕ̕ʎh���ƂȂ��Ă���B�i�����I�A���j �B�I�y���[�^�[�Z���N�V�����i�I���s���j �C�V� �i�T�j�ʓI�w�K����Љ�I�w�K�� �ÓT�I�����Â��ł́C�V�����h���ɓ]�ڂ��邱�Ƃ͉\�ł��邪�����ĐV���������͊w�K����Ȃ��B�I�y�����g�����Â��́u�����I�ڋ߁v��u�����A���v�̎�@�i�s���`���C���i���C�e���C�A�����j��p����Ƃ��܂������ĂȂ����Ȃ��������G�ō��ݓ������s���̌n����ɂ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�������ǂ����������Ȃ��s���ł��邱�Ƃ������ł���B�����͒P�ƂŐ���������̂ł͂Ȃ��B�����ɂƂ��Čo�����瑽���̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ͎����ɈႢ�Ȃ����C������ʂƈقȂ�Љ�I�����ɂ����Đ�������w�K��C����w�K�Ⓓ�̃\���O�w�K�̂悤�ɎЉ�I���ݍ�p�̂��Ƃł������������Ȃ����̂�����B���ɐl�Ԃ̏ꍇ���������͕�w�K��ώ@�w�K����̉e���̕����͂邩�ɑ傫���ƍl�����Ă���B |
 |
 �s����w�̏����_ �s����w�̏����_ |
|
���o�������������̌���
�X�L�i�[�́C�ǂ̂悤�Ȃ��̂��ꎟ�����q�ɂȂ邩���u�����ጸ�v���_�ɂ���Đ������悤�Ƃ����B�����I�ȋ����h����p�i�Q�쓮���C�������Ȃǁj��ጸ������̂��ꎟ�����q�ƂȂ�ƍl������ �C���݂ł́uPremack�̌����v��u�����Ւf�����_�v��u�s���������_�v�ɂƂ��Ă�����Ă���B Premack�́C�̂ǂ̊����������ɂƂ��ċ����q�Ƃ́C���Ȃ̂�����Ƃ������s���Ȃ̂��H�q���ɂƂ��ċ����q�Ƃ́C��������Ȃ̂��C����Ƃ���������ŗV�ԍs���Ȃ̂��ƍl�����B�����āC�u�����s���v�i�Ⴆ�C���ށC�H�ׂ�C�V�ԓ��j�Ɓu�����\�ȍs���v�Ƃ̊Ԃ̐������Ƃ��ĂƂ炦������K�ł���Ǝ咣�����B �@�ނ̌�����v��Ɓu��萶�N�m���̍����s���́C��萶�N�m���̒Ⴂ�s������������B�v �]���āC����s���́C�m���X�P�[����ʼn��ʂ̍s���ɑ��鋭���q�̖������ʂ����C����͊m���X�P�[����ł���ʂ̍s���ɂƂ��ċ��������ƂȂ�B���̂悤�Ȃ��Ƃ���C�uPremack�̌����v���u�����̑��ΐ������v�ƌĂԂ��Ƃ�����B ���̌����ɏ]���C�u��萶�N�m�����Ⴂ�s���́C��萶�N�m���������s������v���ƂɂȂ�B ����𗘗p���čs���Ö@�Ƃ́C�uPremack���̋����q�v���^���C���C�։��Ȃǂ̖]�܂����s���̂��߂̋����q�Ƃ��ėp���邱�ƂɔM�S�ɂȂ����B�uPremack���̋����q�v�Ƃ́C�{��ǂށC�g�����v������C�F�l�ɓd�b��������C�e���r������Ȃǂł���B�]���́C����͂����i�g�[�N���G�R�m�~�[�j��H�ו��ł������B ���炩�ɁC���p�͈͂��L���������Ƃ����������ł��낤�B����ɁC����ɂ���āu�l���v��������邱�Ƃ��ł���B���镪���a�̊��҂ł́C���ꂪ�u�֎q�ɂ����v���Ƃł������B �������Ւf�����_ ���̗��_�́C�uPremack�̌����v�̂���ɐ������ꂽ���̂ł���B�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�ƈ�ʐ����ΐ����_�ɂ��Ȃ߂C�������߁u�����̈�ʐ����ΐ����_�v�Ƃł��Ăׂ���̂�������Ȃ��B ����́C�Q�̍s����������������Ȃ��Ƃ��Ɣ�ׂĐ��������ƁC��萧�����ꂽ�s���͂�萧���̏��Ȃ��s���̋����q�Ƃ��ē����Ƃ����l�����ł���B ���s���C�����_ �u�����Ւf�����_�v�ɂ��C�V�������_�̔��B���h�������B���Ȃ킿�C�u��������Ȃ��i�x�[�X���C���j���Ԃɂ����ē����������̍s����z��������@���C�ł��]�܂������Ԃ��߂������@�ł���v�Ɖ��肷��B���̏�Ԃ��u�����_�v�ƌĂԁB �����̍s�������炩�̃X�P�W���[���̗v���ɂ���Đ����Ƃ��͂��ł��C�ł�����莊���_�ɋ߂Â��悤�ɓ����͂��̍s����z������ƍl����B�Ƃ���C�u�����v�ƌĂ�ł����ߒ��́C���ۂɂ͈�̓���̔��������߂Ă���̂ł͂Ȃ��āC�ނ�����ɂ���ċ������ꂽ����Ɂg�K������h���߂ɍs���̎��Ԃ��Ĕz�����Ă��邱�Ƃ��ƍl������̂ł���B ���̍l�����ɏ]���C�ΘJ�҂����ċx���ɂ��낲�낵�Ă���̂����̎҂ɂƂ��Ă̐V���ȓK���Ƃ��l������B |
 |
 �{���u���b�N�R �{���u���b�N�R |
|
�{������͂��Ă��������B
|
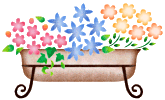 |
 |
 �{���u���b�N�S �{���u���b�N�S |
|
����w�K�S���w�ɂ��C�A����`�Ɋ�Â��s���S���w�I�A�v�[�`�ƔF�m��`�Ɋ�Â��F�m�S���w�I�A�v���[�`�Ƃɕ������C�O�҂͂���Ɂu�ÓT�I�����Â��v����ՂƂ���p�u�����B�A���S���w�i�p�u���t���J�c�Ƃ���Ƃ����Ӗ��j�Ɓu�I�y�����g�����Â��v����ՂƂ���I�y�����g�S���w�ɂQ������܂��B
�܂��������_�Ɋ�Â��s���Ö@�͐l�Ԃ��Ɠ��l�ɍl�������C�l�Ԃ̂����l�ς�F���Ƃ������̂����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ȃ̒����炳�܂��܂ȔF�m�I�v�����d�������w�K���_�����B���Ă��܂����B���̑�\�I�Ȃ��̂��u�Љ�I�w�K���_�v�ł����B |
 |
 ���Z���t�P�A�𑣂��ی��w���̂��߂̍s����w�̉��p ���Z���t�P�A�𑣂��ی��w���̂��߂̍s����w�̉��p |
|
����ł́C�u�i���s���v���ɂƂ�Z���t�P�A�𑣂��ی��w���̕��@�ɂ��ďڂ����q�ׂĂ݂܂��B
�͂��߂� �܂��u�i���v�قǕs���N�Ȑ����K���Ƃ��ĉȊw�I�Ɋm������Ă�����̂��Ȃ��ƌ����Ă悢�ł��傤�B�ɂ�������炸�킪���ł͂���قǗL�Q�Ȃ��̂��K���Ȃ��̔�����Ă���̂ł��B���邢�͒j���̏ꍇ�����ȏオ�i���K���������Ă���̂ł��B�i���͕s���N�ȃ��C�t�X�^�C���̗ʁE���ɂ����Ăm�n�P�ł���C���̍s����ϗe�����邱�Ƃ̓���ɂ����Ă��m�n�P�Ȃ̂ł��B�]���āC�ی��]���҂ɂƂ��Ă��̋i���s���ɑ��闝����[�߂邱�Ƃ�������s���N�s���ɑ���A�v���[�`�̎Q�l�ɂȂ�ɈႢ����܂���B �P�D ���̋i������̂��H �ǂ̂悤�ȍs�����l���鎞�����̍s���������I�Ȃ��̂������łȂ��̂�����ʂ��邱�Ƃ́C�s���ϗe�̓�Փx�ɑ��錩�ʂ��������ŏd�v�ł��B�i���������I�Ȃ��̂łȂ����Ƃ́C���ɂ�鍷�C�����C���ڂȂǂ��l����Ζ��炩�ł��B�ɂ�������炸�C���|�I�Ȑ��̐l���i�������Ă��܂��B����͂ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���H���̂��Ƃ𗝉����邽�߂ɂ́C�i���҂̍s�����ώ@���Ă݂邱�Ƃł��B�i�s�����́j �@ �ʏ�̋i���s�� �i�����邽�߂ɂ́C���R�^�o�R��Ȃ���Ȃ�܂���B�P���P���̐l�Ō��ɂU�O�O�O�~����W�O�O�O�~���x������܂��B���Ɍg�т���K�v������܂��B���̋i���҂̓|�P�b�g�ȂǂɌg�т��Ă��܂��B�Ƃ���ƁC�Q���z���҂́C�ǂ����Ŗ����Ȃ������Ɏ��̂��̂�⋋���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�R���̎҂́C����ɕ⋋���Ȃ���Ȃ�܂���B ���������s�ׂ́C����̔ς킵���������܂��̂ŁC�����i���҂ƌ����Ă��C�P���܂ł̎҂ƂQ���܂ł̎҂ƂR���ȏ�̎҂Ƃł́C�i���s���̘A���̓��e�����Ȃ�قȂ邱�Ƃɗ��ӂ��Ēu���K�v������܂��B���ہC�S�O�{�ȏ�i������҂͂T�������Ȃ��̂����ʂł��B�T�O�{�ȏゾ�ƂO�D�T�����x�ł͂Ȃ��ł��傤���H�R�O�{�z���҂́C�����̒��ɂƂ��Ă��������l�ł��傤�B�命���i�W�O���j�́C�Q�O�{�܂ł̐l�Ȃ̂ł��B���́C�啔���̋i���҂��P���܂łɂ��邱�Ƃɂ͈Ӗ�������̂ł��B�^�o�R�̗����́C�o�ϊw�I�Ɍ��āu�e�͓I�v���ƍl�����Ă��܂��B�o�ϊw�҂͉��i�������Ȃ������ɁC�u���v�v���������������������u�e�͓I�v���ƌĂт܂��B�^�o�R�̗�����{�ɂ���Ƌi���҂̗��͑����ቺ���邱�Ƃ��\�z����܂��B����͉����Ӗ����Ă���̂ł��傤���H�����̋i���҂ɂƂ��āC�i���s���͌����ăj�R�`���ˑ��s���i�n�ȁj�ł͂Ȃ��C�R�[�q�[��g���Ɠ����悤�ɚn�D�Ȃ̂ł��B �A�i���̖w�I��p ����C���̒ʋ̎��]�Ԃɏ��Ȃ���^�o�R���z���Ă���l�����܂��B����́C�A�C�[���N���w�E���Ă���悤�ɁC�ԗl�̕����������Ⴂ�l�Ȃ̂ł��傤�B�A�C�[���N�ɂ��Ɓu�l�ɂ͎h���ɑ��čł�����������K������������C�����h���Ɩ��h���̏�Ԃ�s���Ɋ�����B���̓K�������͂��ԗl�̕��������ƊW������C�l�����傫���v�Ƃ��C�u�T���ē����I�Ȑl���O���I�Ȑl�͖ԗl�̕����������Ⴍ�C�O���I�Ȑl�͊O���h�����邱�Ƃɂ���ēK��������ۂƂ��Ƃ��邪�C�����I�Ȑl�͊O���h����������邱�Ƃɂ���ēK��������ۂƂ��Ƃ���悤�ɓ��@�Â����₷���v���߂ɋi�����i�D�̎h���Nj��̎�i�ƂȂ��Ă���Ƃ����B�i���҂ɋz���Ă���^�o�R�̃^�[���ʂ�q�ˁC���̂���ȏ�ł��ȉ��̃^�[���̃^�o�R�ɂ��Ȃ��̂��ƕ������������h���̓K�����ɂ͌l�������邱�Ƃ��e�Ղɗ��������ł��낤�B���Ȃ킿�C���^�[���E���j�R�`���̋i���҂́C�^�o�R�ˑ��ǂ̌X���ɂ���ƍl������B���̂悤�ȍ��^�[���E���j�R�`���̃^�o�R���z�������Ă���ƁC�u�鉻�v�̑����ߒ��ɏ]���āC���ߒ����������Ȃ邽�߂ɂ���ɋ����h���ً��߂�ƂƂ��ɁC���ߒ����傫���Ȃ��ċz��Ȃ����̕s�����������Ȃ��Ă��邽�߂ɓT�^�I�Ȗˑ����`�����Ă������ƂɂȂ�B �B�i���̓��@ �l�̔��B�ߒ��ɂ����郂�f�����O�i�ώ@�w�K�j�̏d�v���ɂ��Ă͊��q�������C���Ɏv�t���s���̈�Ɂu��l���w�K����v�s���Ɓu���s�v�ɕq���Ƃ������Ƃ���������B ���Ȃ킿�C���̎����ɋi���s�����u���ȋ�����v�̃��p�[�g���[�ɑg�ݍ��܂��̂ł���B���͂Ɉ�؋i���s�������Ă���҂����Ȃ����ň�����҂ɁC�����i���s���������\���͒Ⴂ�ł��낤�B���́C�e���r���y�⒇�Ԃ̍s���́u��l���ۂ��v�u�������悳�v����ώ@�w�K�ɂ���Ċw�K����̂ł��낤�B�ώ@�҂ł���q���́C�i�����Ă��郂�f���ɒ��ڂ��C���f���̎Љ�I�]���i�������悳�Ȃǁj���㗝�����ƂȂ��Ė{�l���i�����n�߂�B�߂������̋i������\�z����ɂ́C���w���⒆�w���ɃA���P�[�g��������悢�B���݂̒��w���B�́C�u���w���̋i���s���ɔے�I�ł�����̂́v�u��l�̋i���s���Ɋ��e�ł���v���Ƃ��m���Ă���C����璆�w�����i���\���Q�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �C �C���]�� �u���炢�炷��Ƃ��Ƀ^�o�R���z���Ƃق��Ƃ���v�Ƃ����̂́C�^�o�R�̖w�I��p�ȊO�Ɂu�F�m�Ö@�v�ł����u�C�̂��炵�v�����ʓI�ɍs�����Ƃ��ł��邩��ł���B ����ɁC����f�����Ƃɂ��ċz�@�ɂ��u�����N�Z�[�V�����v���ʂ�����ɈႢ�Ȃ��B���ہC����X�g���X���ŋi�������ɗ����Ƃ�����Ƃ��̎�ϓI�������̂��̂��i���̌���I���@�ɂȂ邱�Ƃ�����Ă���B �����������Ƃ���C�����͂P�Q�{���ቺ�����ɂ������Ƃ��m���Ă���B �s����w�̌�������́C����Ɍ��ʂ��Ă������Ƃ����z�I�ł���ɂ�������炸�C�����̌����҂͎��s���C�։������҂̌o������͐߉��������S�f������ł���Ƃ��������Ă���B�P���ɕW���l�H�i�������ł���P�z�����ԂQ�b�C�z���Ԋu�T�W�b�C�P��z�����ԂW���C�S�O�����i���̎��ԊԊu�ŋz�������Ȃ�j�ɋi������Ƃ��ĂW���ԂłP�O�{�̌v�Z�ɂȂ�B���́u�s���C�����_�v���痝������邱�Ƃ́C�i���҂ɂƂ��āC�P���P�Q�{�̋i��������Ƃ����s���͂P���ɂP�O�O���߂��́u�C���]���v�����Ă��邱�Ƃ������Ă���C��x���̐������Y���Ɋ���Ă��܂��ƋC�Â��Ȃ������ɂP���̎��Ԃ̂P�O�O�����i�����Ԃɔz������悤�ɂȂ�B �Q�D �i���҂̔F�m�Ƒԓx �@ �F�m�I����̊m�� �i���҂́C�����ɑ��ĔF�m�I�ɕs���a�ȏ�Ԃ���E�o���邽�߂Ɏ�Ɏ��̂悤�Ȏ�@���Ƃ��Ă���B �E ���݂ɖ�������F�m�v�f�̈�����̂Ȃ��悤�ɕω�������B���������z��Ȃ��l������ɂȂ�B �E ���a�I�ȏ���V���ɉ����遨�A���c�n�C�}�[��p�[�L���\���a��咰����ɂȂ�ɂ����B �E �����̔F�m�v�f�ƕs���a�ȊW�ɂ�������������B�������͘c�Ȃ��ĉ��߂���B �E �s���a�ȔF�m�v�f�̎����ɂƂ��Ă̏d�v�x���߂�B �A ����̏��� ����i���҂͐��̒��̈��҂ɂ���Ă���̒��ŋi���𑱂��Ă������߂ɂ͂���ɋ��łȖh�q������K�v������C�u����̏����v�Ə̂���Ă���B �u����v�F�Љ�I�K�́��u�i���͌��N�ɗL�Q�ł���v���i���҂́u�F�ɏ]��Ȃ������ �l�ԁv���u�ǂ����ُ�Ȑl�ԁv�Ȃǂ̃��b�e�� �E �u�{���͈ӎu�̗͂ł��ł��։��ł���̂��v�Ǝ咣 �E �t�Ɏ������g���u��p�ҁv�ƕW�Ԃ��C���\�͂����������邱�Ƃɂ��ӔC������悤�Ƃ���B �E ���邢�́C�^�o�R�̖{�����߂ċK�͂ɑ��Ă͈ᔽ���Ă��Ȃ��Ɖ��߂���B ���̂悤�ɍI��������̏��������Ă��邽�߂ɁC��w�I�m���ł����ċi���̗L�Q������ ���I�ɉ����t���Ă����i���҂̒�R�͗e�Ղɂ͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B �R�D �i���w���͂ǂ�����ׂ��� �@ ��w�I�؋� �i���́C�����̐g�̂ɗL�Q�ȉe���������Ƃ��m���Ă��邪�C��ȉe���� �E ���K���ւ̉e�� �E �z�펾�����ǂւ̉e�� �ƕ����čl���邱�Ƃɂ���B �܂��C�������Ƃ���łȂ��u�j�R�`���́C�s����}���C�{���}���Ďd���𑣐i������\�͑��i��p������Ă���C���ɔ�ނ̂Ȃ������ł���B�v�i�E�H�[�o�[�g���P�X�W�U�j��p�Ƃ������Ƃ�����Ă���B ����C��^�[���ɂ��x����̃��X�N�Ƃb�n�o�c�i�����ǐ��x�����j�̜늳�͒��������P�������̂̋������S�����ɂ��Ă͂قƂ�lj��P���Ȃ��Ƃ����B�K���������S�����̋ɂ߂ď��Ȃ��킪���ɂ����ẮC���Ƃ��։��ł��Ȃ��Ă���^�[���ɐ芷���邱�Ƃɂ�鉶�b�͂͂���m��Ȃ����̂�����B�i�x����̎��S������ʂł��L�����Ȕx���f�����݂��Ȃ��j �A ���^�[���ʂ̒ጸ���@ ���^�[���ʂ����炷���@�́C�{�������炷��������^�[���^�o�R�ɐ芷���邱�Ƃł���B�����̌��_�͐�q�����悤�ɂP�Q�{���ቺ�����ɂ������ƂƁu���Ȓ��߁v�i�[���z�����ނ悤�ɂȂ�j�ɂ�肩�����ĔA���ψٌ������̗ʂ���������ƌ����Ă���B����C��^�[���̃^�o�R�ł́C�{��������������ʂƂ��Ċe��f�[�^�i������_���Y�f�Z�x�Ȃǁj�ɍ����݂��Ȃ��ƕ���Ă������ߔN�ɂȂ��Ē���^�[���̃^�o�R���o�ꂷ��悤�ɂȂ�C��i���{����������҂����邪�唼�͋i���{���ɍ��͂Ȃ��L�ӂɊe��f�[�^�����P����邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B�i���Ȓ��߂ɂ���Ė{�����������đ�����Ƃ����S�z�����邪�C���̂�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����������j ���C�킪���̂����̕��σ^�[���ʂ͂P�X�V�O�N�Q�Omg�C�P�X�W�W�N�P�Rmg�������������݂͂��悻�����ɂ܂Ō������Ă��邱�Ƃ����肳��Ă���B �B �։������҂̓��� �։������҂̑����́C��^�[���C��{���ł��������Ƃ��m���Ă���B �܂��u�����I�v�u���I�����X���v�̎҂������B �C �։������� �i���҂̖�V�����^�o�R����߂����Ǝv���Ă���C���̂V�O�������ۂɋ։������s���邪�C�唼�͎��s�ɏI���C�։����ێ����Ă���҂��i���������Ǝv���Ă���҂����Ȃ肨��C���̂悤�Ȏ҂̃^�C�v�́u���y�^�v�Ɓu�h���^�v�ł���Ƃ���������B �ł������։��������łR�O������Ă���Ƃ����Ă���B����́C�։��̈ӎu�������҂�Ώۂɂ����f�[�^�ł���B���R�̋։����͂S�����x�C��t�ɂ��ȒP�Ȏw���̋։����łV�`�W���Ƃ����Ă���B �S�D �i���w���ɑ���s����w�I�A�v���[�` �@ �i���҂ɑ��闝�� �i���҂ɂƂ��ċi���s���͔��ɋ��������q�ƂȂ��Ă��邽�߂��̍s�����������邱�Ƃ͍���ł���B�i�v���}�b�N�̌����ɏ]���C�i���s���ȏ�̋����q�𐏔�������K�v������B�j �A �i���҂̍s���̗\�� �u�w���X�E���[�J�X�E�I�u�E�R���g���[���v��u�Z���t�G�t�C�J�V�[�v��u���l�ρv�i�����q���p�[�g���[�j��m��B���I�����X���̎҂قǕی��s�����Ƃ�₷���B �B �s���S�̂̃o�����X���l���� �u�����Ւf�����_�v��u�s���C�����_�v����l�͍s���z���Ă��邽�߁u�։��v�s���́C�V�X�e���̃A���o�����X�ށB��������܂�������邽�߂ɂ́C���̂Q�̕��l������B �i�`�j�։��{�i���s���ȏ�̋��������s���𑝂₷�B ���u�����^�o�R����߂�Ƃ�����Ɛh�����C�ǂ����������߂�Ƃ���� ����^�o�R��߂܂��v�Ƃ����ꍇ�̂悤�Ɂu�����v�s���Ȃǂ�������B�i�ܘ_�C �l�ɂ���āu�����v�łȂ��ʂ̍s����������Ȃ��j ���ۑ��C�։��҂ɂ����āu�����v�s���̑��傪�ώ@����Ă���B�h�����̂��� �H�ו��ł��悢��������Ȃ��B �i�a�j����^�[���^�o�R�ւ̐�ւ� �i���҂ɂƂ��āu�i���s���v�́C��̃V�X�e���i�����̘A���j�ł���ƂƂ��� �S�s���̒��ň��̃G�l���M�[�z����Ă���B�����̘A���̒��ł́C�����q����ł��������������₷�����ƂƁu�I���s���v�̐�s�S���𗘗p���āC����^�[���̃^�o�R���ʂɍw������悤��������B��������Ƒ��̂��ׂĂ̋i���s���̘A���͓����Ȃ̂ŃV�X�e���Ƃ��Ĕ��Ɉ���x�������B�i���{����������Ƃ���Ί����̗v���ɕω��������Ă��邽�߂ŁC�i���{���������邱�Ƃ́u�v���}�b�N�̌����v����l���Ă��\�����Ⴂ�ƌ�����B�������āC���炭�u����^�[���i���v�𑱂��Ă��邤���Ƀj�R�`���ˑ����ጸ���u�։��v����҂��łĂ�����̂Ɗ��҂����B�i�� �̊ϓ_���猾���C�u�@�\�I�ʉ��v�F�։��p�C�|�ɋ߂��Z�@��������Ȃ��j �C���� �u�h��������v�̗��_���炷��C�i���s���Ƃ�����̏�ʂƂ��A�������邱�Ƃ��d�v�ł���B���ԂƊy������b�ł���悤�ȁu�i���R�[�i�[�v�ƌ����ĘA�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���X�g�����ɂ����Ă��w�ɂ����Ă���Ђɂ����Ă��ɂ߂Ă��т����S�I���ƘA��������ׂ��ł���B�L���̃l�b�g���[�N�̍č\�����i���X�g���j �P���Ԃ̌��N����̒��Ŗ�P�O���̋i���w�����s������P�N��̌��ʁB �P���Ԃ̌��N�����ɂ�����P�O���̋i������̌��ʁi��^�[���w���𒆐S�ɍs���Ă���B�W�c�w���j ����C ���N�f�f�̋����~�������Łu�v���������v�ƂȂ��Čċz��O������f�����҂Ōy���Ȉُ�݂̂łP�N��̌o�ߊώ@�Ȃ����҂U�U���ɑ��āC�T���̋i���w�������{�����̌��ʂ��P�N��ɋi���ƌg�т��Ă���^�o�R�ɂ���Ċm�F���s�����B�Ώۂ̓��ꐫ��������̂̋ɂ߂č������ʂ��B�܂��ی��w�ɂ���čs�����E��ɂ�����i���w���ɂ����Ă����l�̌��ʂ��B �܂Ƃ߂�ƁC��^�[���w���ɂ��e�Ղɍs���ϗe������ꂽ�B ��^�[���̖����ɕύX��ɂ����Ă��i���{���͕ς��Ȃ������B �s����w�I�ɃV�X�e���Ƃ��Ĉ��肵�Ă���w���ł��邱�Ƃ� �s�������̉��������Ƃ����ʓI�ł������悤�Ɏv����B�܂��C�։������҂̑唼�͊��ɒ�^�[���ł������B�܂��C�i�����P�s���͓��I�����X���ɂ��݂��C���ɋ։��҂ɂ����Ă͗L�ӂł������B |
 |
 �����N�W �����N�W |
 �F��@�G���̃z�[���y�[�W �F��@�G���̃z�[���y�[�W |
|
 @nifty @nifty |
@nifty�̃g�b�v�y�[�W�ł��B
|
 �T�N�T�N�쐬�N �T�N�T�N�쐬�N |
�J���^���z�[���y�[�W�쐬�c�[���B
|
 |
| HOME�b�p�[�\�i���e�B�ƌ��N�b�s����w�T�u�e�L�X�g�b�v���t�B�[���b�Y�ƕی��b�ی��w���b���B�s���b���̍u���E���C�b�l���ƌ��N�b���q�_�o�s���w�������b���q�_�o�s���w�b����@��w�����Ȍ��N���i�E�s���w |
|
